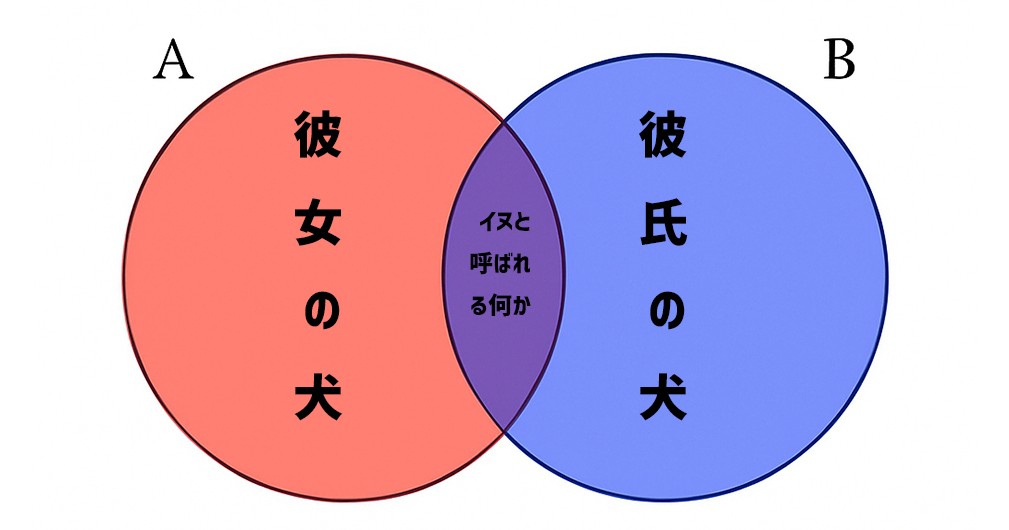写真のテーマと自己欺瞞
大雪の日の新幹線からこんにちは。現在新富士に向かっています。昨日から関西と関東の交通が寸断されていて、本当は車で行く予定だったのですが新幹線に変更。その新幹線も雪の影響で低速運転中。いつもよりゆったり走る新幹線から書いております。

京都を出て滋賀の東側を走る新幹線の車窓から。雪雲の上には綺麗な青空が広がっているものです。
今日は少し個展のことを離れて写真家について考えています。と言うよりは、写真のテーマかな。いや、ほんと言うと個展と関係あるんです。幾つか前のレターで「個展をやる理由」みたいなことを書いたんですが、結局その根底には「写真家ってなんだろう?」という問いが横たわっていました。
そう、写真家。字義的には今更問うまでもない簡単な話で、写真を撮る人です。ここにはアマもプロも含まれるのでしょう。写真を撮る人は全て写真家と呼ばれていいと思うのです。それにもかかわらず、僕自身が長いこと自分のことを写真家と思えなかったこと、今になってさえ、「写真家」と名乗ることに一種の抵抗感を感じることの根底には、この一見シンプルな定義「写真家」には、その明快な定義とは正反対の、ある種の自認を難しくする要素が介在しているのではないか、そんなふうに感じるんですね。
ややこしい書き方していますね、ごめんなさいね。最近個展が近づいているせいで、思考が若干いつもより深めのところを漂っています。そうこうしているうちにさっきまで雪の後の快晴だった空は、再び強烈な雪雲に包まれ始めました。今回の寒波はなかなかの規模ですね。

米原から岐阜羽島あたりを走っている時の車窓から。岐阜との県境を作るこの辺りは、山が深くて天候が変わりやすいです。
そう、写真家。僕は風景を撮るので、サブジャンルをさらに細分化すると、風景写真家ということになります。かつて僕は自分のそういう浮き草的な自認の難しさをある程度「港」に留めるためのアンカーとして、「Around the lake」というテーマを無理くり捻り出しました。直訳すると「琵琶湖周り」ですね。なんということもないテーマなんですが、これには随分助けられました。対外的にも伝えやすいですし、居住地の近くを撮影地にすることで、何を撮ってもなんとなく体裁が整うような気がしたんです。
でも今「体裁」と言いましたが、そう、それはもともと最初のグループ展示の時に急造で考えだした苦し紛れのテーマだったんです。周りを見るとみんなかっこいいテーマで写真を撮ってたので、何か僕も必要だと思って、とりあえず英語で言ったらかっこいいんじゃないか、そんなノリで出来たテーマです。でも、そのままずるずると10年近く使い続けることになりました。
もちろん、名は体を表すという言葉もある通り、外形を整えてしまえば内面が整うというのはよくある話です。というか、僕はもともとそういう考え方をする人間です。テーマなどという極めて自己言及的かつ自己欺瞞的な考え方はあまり好まないんですね。他人はいざ知らず、僕は自分が欺瞞的な人間であることを百も承知しているので、そういう「自己設定」はフィクションに過ぎないと考える人間です。好きなことを好きなようにただやればいい、外面はそのうちついてくる、そう考えがちな人間なんです。だからテーマなんて考え方とは、そもそも折り合いが極めて悪い。
余談ですが、だから就職活動でいうところの「自分探し」に対しても懐疑的な目線を向けがちです。探して見つかるような自己くらいなら、22年も生きてたら普通に見つかると思うんですよね。「自分探し」というあの壮大なフィクションは、つまり、社会、あるいは会社が求めるような括弧付きの「自己」の定義を自ら物語ってみせる、一種の厚顔なほどの演出性への適性を見ているのではないか、と僕などは思っているわけです。もうそういう世界も終わるのかもしれませんが。
閑話休題ですね。そろそろ名古屋に近づいてきました。こちらはそんなに雪が降ってなかったようです。

名古屋のちょっと手前で見えたお城。名古屋城ではなさそうです。
そういうわけで、本来テーマなんてものにはあまり興味がない僕にとってはAround the lakeという、苦し紛れに捻り出したテーマは、ちょうど良くすっぽり僕の「外見」を作り出してくれました。そして10年ほどはそれでよかったんです。外面に対して自らを擦り合わせていくのに、それほどの無理は感じませんでした。
ところが、ふと最近気づいたんです。僕全然、地元撮ってない。地元どころか、まともな風景も撮ってない。そもそも僕はこの10年も、地元を撮るというよりは、梅、桜、花火、飛行機、紅葉、雪をとって、あとは寝ているような10年を過ごしてきました。極めてテーマ的に狭い場所に自分の作品群を置いてきたんですね。それが最近はさらに少なくなってきた上に、本来、それらの狭い被写体の間のシーズン、いわゆる風景クラスタにおける「写真のオフシーズン」には地元を駆け巡るべきだと思うのですが、そう言うオフシーズンには最近はすぐに海外に行きます。だって海外が楽しいのですもの。自分に嘘はつけません。
ことここに至ってついに、自分が10年前に設定した外面的なテーマと、現在の行動との乖離が目立ってきました。その乖離が、僕のゴーストにそっと囁くんです。
「君が自分で写真家という時、その足はどこに立脚しているのか?」
これまでは「多少のずれは誤差の範囲」と敢えて目を逸らしてきた部分から、さすがの厚顔無恥を自認する僕も目を逸らせなくなってきました。そうこうしているうちに回ってきた2度とないような格式の高い個展の話。なんというか、そろそろ僕は考えねばならないらしい、そう観念したのが昨年あたり。そしてようやく自分なりの答えを見つけたんですね。
僕は多分「世界の理解」をしたいんですね、写真とカメラを使って。
気づいた時、「なあんだ」と思いました。これ、子どもの頃からずっと変わらずの欲望なんです。わかりたい、理解したい、自分の目で。大学院もその研究でした。その慣れ親しんだ欲望が、かつては自分の家の周りにだけ向いていた時は「Around the lake」でことは済んでいたのですが、その目線が外に向かった時、やりたいことと外面的に設定したテーマがずれ始めた、それがことの真相だったのだなと。
そうわかった時、やはりコロナの影響は随分大きかったなと気づきました。動きそのものを物理的に封じられた3年間は、おそらく僕の心に相当な負担だったのです。「外へ目を向けること」に対する強烈な内圧が知らぬ間に僕の心に強烈な外向きのベクトルを加えていたのです。行くことのできなかった場所を自らの目で見てみたい、もしかしたらまた見られなくなる日が来ないとも限らない、その欲求とある種の恐怖が、自分の動きを、目を、写真を、外へ外へと向ける圧力になったのです。

名古屋から三河安城を抜けるあたりの車窓の風景。雪の気配はもうすっかりありません。
というわけで、ようやく自分が写真を通じてやろうとしていることの根本的な欲求がわかったのがつい最近ということなんです。でもこれも結局、今回のこの発見が「コロナ禍の影響」にあったことを自覚したように、いつだって外部からの影響によって変化が加わっていくだろうと思うのです。その意味では、やはり人間の内面というのは、むしろ外的な刺激から形作られていくのだなあということを改めて実感するし(つまり内面とか個性などというものはフィクションなんです)、その意味ではかつて僕がAround the lakeというテーマを掲げたことも、それなりにずれてはいなかっただろうなと今更感じます。
というよりも、一周回ってようやく、目が外に向いているからこそ、足元の着地点としての地元の風景というものが、近い未来で見え始めてくるのではないかという予感ができ始めているのですね。旅に飽く頃、今度は目線がまた近い場所に向くのかもしれません。
というあたりで、そろそろどうやら新富士に到着しそうです。撮影準備ですね。いい写真が撮れますように。
すでに登録済みの方は こちら